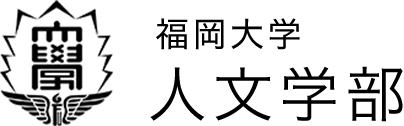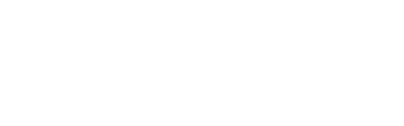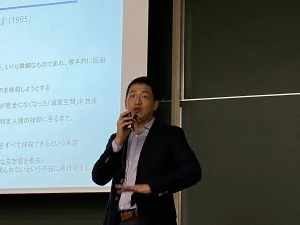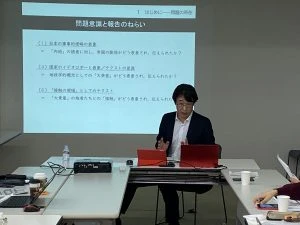学科トピックス
2019.10.26
【報告】第3回 福大韓国学シリーズ(10月18日[金]-19日[土])
10月18日(金)には、「他者なき民主主義:現代韓国の長期民主化とそのディレンマ」というタイトルで、金杭氏(キム・ハン、延世大学[韓国]・副教授)の講演会が行われました。
1987年の民主化抗争以降における韓国の民主化の過程を通じて、民主主義が持つ特性とその限界についての話でした。民主主義社会において「正常」状態を想定し、その「正常」という基準から離れた存在を嫌悪・排除する民主主義のディレンマ的な状況についての講演でした。多様性と寛容に基づいた民主主義を語り、そのなかで生きていきながら、はたして「正常」ではないと見なされる存在と、我々はどのように接して共に生きていくのか。こうした問いを、日本と韓国という自由民主主義の社会を生きる我々に問いかけた話でした。
10月19日(土)の午後には、若手研究会が行われました。
田中美佳氏(九州大学大学院博士課程)は「1910年代における出版社新文館の刊行物:日本の出版界との関係を中心に」というタイトルで、20世紀初頭の韓国の児童雑誌の問題を、1910年代に新文館から刊行された児童雑誌と当時日本の博文館より刊行されていた雑誌との相関性や差異についての話でした。
金牡蘭氏(キム・モラン、早稲田大学韓国学研究所・招聘研究員)は、「朝鮮演劇という参照項:村山知義の解放前後について」というタイトルで、朝鮮の解放(1945年8月)前後に朝鮮に滞在していた村山知義の経験と日韓演劇の影響関係についての話でした。
林惟卿氏(イム・ユギョン、延世大学[韓国]・HK研究教授)は、「韓半島の冷戦と社会主義の文化企画:1945年から1950年代にかけての北韓の冷戦機構と文化企画者たち」というタイトルで、解放後(1945年以降)の北朝鮮知識人のソ連紀行を中心に、北朝鮮の文化企画とソ連との関係性、ひいてはそれを模倣していた南の韓国の問題についての話でした。
最後に他分野研究者(日本文学・文化)として五味渕典嗣氏(早稲田大学・教育・総合科学学術院・教授)は、「接触と包摂:アジア・太平洋戦争期における「大東亜」の心象地理」というタイトルで、太平洋戦争期における大東亜の表象の問題を、戦争の拡大と「大東亜」の概念の具現化が連動する運動としてのものだったことについての話でした。
今回の若手研究会では、1910年代から1950年代にかけての朝鮮半島ひいてはアジアにおける諸文化が、出版、演劇、戦争、旅行というキーワードで、互いに交差していた様子を確認することができました。
1987年の民主化抗争以降における韓国の民主化の過程を通じて、民主主義が持つ特性とその限界についての話でした。民主主義社会において「正常」状態を想定し、その「正常」という基準から離れた存在を嫌悪・排除する民主主義のディレンマ的な状況についての講演でした。多様性と寛容に基づいた民主主義を語り、そのなかで生きていきながら、はたして「正常」ではないと見なされる存在と、我々はどのように接して共に生きていくのか。こうした問いを、日本と韓国という自由民主主義の社会を生きる我々に問いかけた話でした。
10月19日(土)の午後には、若手研究会が行われました。
田中美佳氏(九州大学大学院博士課程)は「1910年代における出版社新文館の刊行物:日本の出版界との関係を中心に」というタイトルで、20世紀初頭の韓国の児童雑誌の問題を、1910年代に新文館から刊行された児童雑誌と当時日本の博文館より刊行されていた雑誌との相関性や差異についての話でした。
金牡蘭氏(キム・モラン、早稲田大学韓国学研究所・招聘研究員)は、「朝鮮演劇という参照項:村山知義の解放前後について」というタイトルで、朝鮮の解放(1945年8月)前後に朝鮮に滞在していた村山知義の経験と日韓演劇の影響関係についての話でした。
林惟卿氏(イム・ユギョン、延世大学[韓国]・HK研究教授)は、「韓半島の冷戦と社会主義の文化企画:1945年から1950年代にかけての北韓の冷戦機構と文化企画者たち」というタイトルで、解放後(1945年以降)の北朝鮮知識人のソ連紀行を中心に、北朝鮮の文化企画とソ連との関係性、ひいてはそれを模倣していた南の韓国の問題についての話でした。
最後に他分野研究者(日本文学・文化)として五味渕典嗣氏(早稲田大学・教育・総合科学学術院・教授)は、「接触と包摂:アジア・太平洋戦争期における「大東亜」の心象地理」というタイトルで、太平洋戦争期における大東亜の表象の問題を、戦争の拡大と「大東亜」の概念の具現化が連動する運動としてのものだったことについての話でした。
今回の若手研究会では、1910年代から1950年代にかけての朝鮮半島ひいてはアジアにおける諸文化が、出版、演劇、戦争、旅行というキーワードで、互いに交差していた様子を確認することができました。
【文責:柳忠熙】
講演会の様子
若手研究会の様子