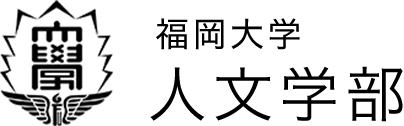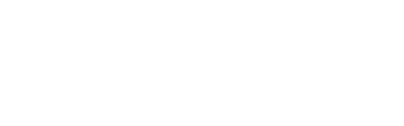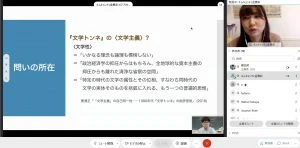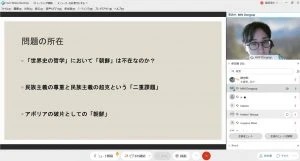学科トピックス
【報告】第4回 福大韓国学シリーズ(10月23日[金]-24日[土])
10月23日(金)、24日(土)に第4回福大韓国学シリーズを開催された。福大韓国学シリーズは、韓国学関連で日本、韓国そしてほかの地域の研究者が集まって話し合う集まりである。特に福岡で集まるということを考えてこれまで4回開催してきた。今年はコロナ禍の影響で韓国とアメリカの研究者が日本への入国ができなかったこともあり、オンライン講演会と研究会という形で行われた。
10月23日の講演会では、申明直氏(シン・ミョンジク、熊本学園大学)が「在日コリアンの省察と 疎通:映画「月はどっちに出ている」を中心に」というタイトルで、梁石日の作品を原作とした「月はどっちに 出ている」を手掛かり戦後日本社会における在日コリアンについての話であった。講演の前半はサンフランシスコ条約によって朝鮮国籍として外国人となった在日コリアンの状況、日立製作所の就職裁判、外国人押捺問題、ゲットー(ghetto)化された在日コリアン社会などの問題に関連して「血と骨」などの映画を例として挙げ、在日コリアンの歴史と社会的背景についての話であった。後半は70~80年代における在日コリアンの様相を「月はどっちに出ている」を通じて探り、複層的な在日コリアンのアイデンティティーの問題、日本社会における在日コリアンの立ち位置の問題、在日コリアンとフィリピンなどの在日外国人との関係についての話であった。全体の講演を通じて多国家市民(権)というテーマを考える時間であった。
10月24日の若手研究会では4人の研究者が発表を行った。まずは鄭基仁氏(チョン・ギイン、ソウル科学技術大学)の「詩、詩歌、poetry 韓国近代詩の形成と漢文脈、国脈、欧文脈という三重文脈の乱脈像:李光洙の詩論を中心に」は、金億(キム・オク)の詩と杜甫の漢詩との形式的な関連性とこの事例をもって李光洙(イ・グァンス)をはじめとする近代朝鮮初期における文学者たちの詩論の問題に関する話であった。次に金景彩氏(キム・ギョンチェ、武蔵大学)の「〈文学性〉の発見と植民地という問題 : 金基鎮の文芸批評を中心に」は、金基鎮(キム・ギジン)の文学観、特に社会主義イデオロギーと文学性の問題についての発表であった。続けて閔東曄氏(ミン・ドンヨプ、学習院大学)の「〈世界史の哲学〉と植民地朝鮮:「民族の哲学」をめぐる一試論」は、京都学派である高坂正顕と三木清が行った対談「民族の哲学」(1941)を通じて民族についての二人の観点と、二人の議論のなかで朝鮮民族の問題が語られていないことを確認した発表であった。最後にシム・ミリョン氏は(ジョジア大学)「戦時植民地朝鮮文学に表れる“アジア”と“帰還”」は、李孝石(イ・ヒョソク)の日本語小説「ほのかの光」(1940)を分析対象とし、高句麗の剣をめぐる博物館側と持主の郁(ウク)の葛藤を通じてアジア主義と誤読の問題についての話であった。
【文責:柳忠熙】
講演会の様子
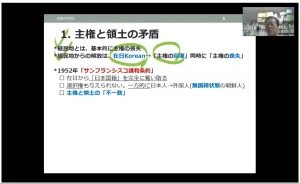
若手研究会の様子