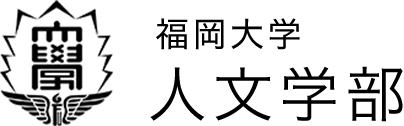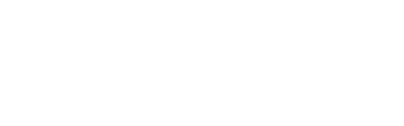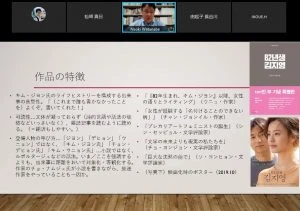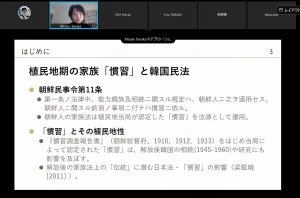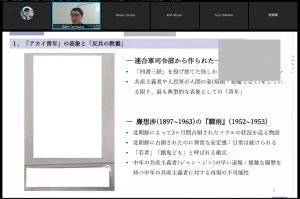学科トピックス
【報告】第6回 福大韓国学シリーズ(10月22日[金]-23日[土])
10月22日(金)、23日(土)に第6回福大韓国学シリーズを開催された。福大韓国学シリーズは、韓国学関連で日本、韓国そしてほかの地域の研究者が集まって話し合う集まりである。特に福岡で集まるということを考えてこれまで開催してきた。今年度は、昨年度同様に、コロナ禍の影響で韓国の研究者が日本への入国ができなかったことや国内移動の自制などもあり、オンライン講演会と研究会で行われた。ただ講演会は、すでに福岡大学では対面授業を行っていることもあり、三つの教室から同時に接続を行うなど、オンラインではあるものの、学生たちも参加しやすい形で行った。
10月22日の講演会では、渡辺直紀氏(武蔵大学)が、「韓国文学とフェミニズム」というタイトルで、チョ・ナムジュの『82年生まれ、キム・ジヨン』をはじめとする、日本における韓国文学のブームとその背景との言えるフェミニズムの問題を、韓国文学の作品と解放後(1945年)の朝鮮半島の歴史的な文脈を示しながら説明した。時代において韓国の男性作家と女性作家の女性や社会を見る眼差しの差異についての話が印象に残った。韓国が独裁政権の下で産業化を押し付けていた状況で、男性作家の女性に対する女性への視線が自由奔放な女性像を描きながらも遊ぶ女などの男性の先入観の枠内で描かれている。一方、韓国の民主化後の1980年代後半から90年代に入り、女性作家の活躍が目立つことになり、自分だちの話を自ら語るようになったことである。それが現在にも続いており、日本ひいては世界に社会における男女の問題・LGBTQなどを考えるきっかけを与えている。
10月23日の若手研究会では、3人の研究者が発表を行った。
まず、田中美彩都氏(西南学院大学)の「慣習調査史料(1908~1909)からみた近代朝鮮における養子「慣習」の形成過程」は、朝鮮時代の家族関係、特に養子に関する慣習に関する諸家族問題が朝鮮総督府によって調査され、その結果をまとめた『慣習調査報告書』の編纂過程とその意味についての発表だった。朝鮮総督府の近代的な民法制度の植民地朝鮮への適用、日本の家制度における養子の問題と朝鮮の伝統的な養子制度などの齟齬の問題から植民地期の同化政策の問題までいろいろと植民地統治という諸問題を考えさせる内容だっだ。
次に、潘在泳氏(バン・ジェヨン、韓国・高麗大学校大学院博士課程)の「成長の困惑:戦後韓国における「反共の教養小説」を巡って」は、朝鮮戦争(1950~1953年)後に出た小説(例:鮮于煇[ソニ・フィ]「焔」 、崔貞熙(チェ・ジョンヒ)『人間史』など)から反共の表象の問題についての発表だった。朝鮮戦争後、新生自由民主主義国家である南の大韓民国において反共が唱えられる状況のなか、左翼の若い青年たちの表象に注目し、彼らを自由民主主義の観点から啓蒙の対象として位置づけられていたことが興味深かった。
最後に、韓国学と他分野との研究交流の旨として発表をお願いした田中雄大氏(東京大学大学院博士課程)の「中国「モダニズム」詩論における個性の問題」は、近代中国のモダニズムについての観点を1920~40年代に活躍した廃名や李健吾などを中心とする発表だった。今回の発表は、上記の二人の前世代(胡適、郭沫若など)の近代中国のモダニズムの有り様を批判あるいは再考することでもあり、1980年代に入ると、この廃名や李健吾などが古典的モダニズム論者と理解されるなど、中華圏における地域や時代によってモダニズム論の変容を考えさせる内容だった。
今回は議論を中心とするために上記の3名の若手研究者にお願いしたが、コメンテーターの渡辺直紀氏(同上)、金牡蘭氏(キム・モラン、早稲田大学・韓国学研究所)、閔東曄氏(ミン・ドンヨプ、学習院大学)から、上記の感想などに関する3名の発表者に様々な角度から質問とコメントがなされ、予定時間を過ぎるなど、熱烈な議論が行われた。
来年度は可能であれば、海外・国内の研究者らを福岡に招聘し、講演会と若手研究会を含めた大規模の国際シンポジウムを企画している。
コロナ禍が治まり、福岡で皆が集まって話し合えることを心より祈る。
【文責:柳忠熙】
講演会の様子
若手研究会の様子