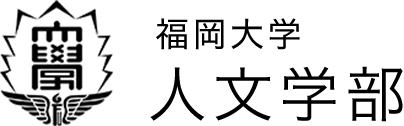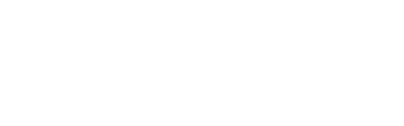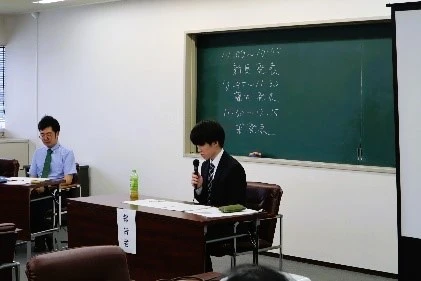学科トピックス
2025.10.22
第27回七隈史学会のレポート①です!
こんにちは、日本史教員の山田です。10月も後半となり、九州もずいぶん秋めいてきました。
さて、今回から3回にわけて、9月27日(土)・28日(日)に開催された第27回七隈史学会大会の様子をレポートします。まずは、外国史部会の様子からです。以下、大学院生が書いてくれたレポートです。
さて、今回から3回にわけて、9月27日(土)・28日(日)に開催された第27回七隈史学会大会の様子をレポートします。まずは、外国史部会の様子からです。以下、大学院生が書いてくれたレポートです。
外国史部会の様子をお届けします。午前は個別報告が3本あり、午後はシンポジウムとして3名の報告者にご登壇頂きました。
〇午前の部
まず、新貝 隼士さん(福岡大学・院)に「北朝隋唐期の庫真・親信・帳内-「兵」としての一考察-」という題目でご報告いただきました。6世紀の中国で、皇帝を凌ぐ権力を持った臣下や皇族が有したボディガード「庫真」「親信」をより広く「兵」という概念で捉え、彼らが宮廷クーデターに関与した姿や廃止の理由を明らかにされていました。
次に、藤丸 祐大さん(福岡大学・院)に「ルネサンス期イタリアの生殖と医療」という題目でご報告いただきました。イタリア・フェラーラの宮廷侍医ジョバンニ・ミケーレ・サヴォナローラが記した産婆術書『妊婦と7歳までのこどもの養生』を読み解き、ルネサンス期のイタリア都市社会における性と生殖の言説分析を課題として、考察されました。
午前の部最後は、梁 躍雲さん(大阪公立大学・院)に「宋元時代における駆蝗神信仰の変遷」という題目でご報告いただきました。宋代に頻発した自然災害の中でも、特に深刻な脅威だった蝗害に対応して出現した「駆蝗神」への信仰を考察されました。国家儀礼から地方祭祀へ、そして自然神から人格神への変化というプロセスについても、論究されていました。
〇午前の部
まず、新貝 隼士さん(福岡大学・院)に「北朝隋唐期の庫真・親信・帳内-「兵」としての一考察-」という題目でご報告いただきました。6世紀の中国で、皇帝を凌ぐ権力を持った臣下や皇族が有したボディガード「庫真」「親信」をより広く「兵」という概念で捉え、彼らが宮廷クーデターに関与した姿や廃止の理由を明らかにされていました。
次に、藤丸 祐大さん(福岡大学・院)に「ルネサンス期イタリアの生殖と医療」という題目でご報告いただきました。イタリア・フェラーラの宮廷侍医ジョバンニ・ミケーレ・サヴォナローラが記した産婆術書『妊婦と7歳までのこどもの養生』を読み解き、ルネサンス期のイタリア都市社会における性と生殖の言説分析を課題として、考察されました。
午前の部最後は、梁 躍雲さん(大阪公立大学・院)に「宋元時代における駆蝗神信仰の変遷」という題目でご報告いただきました。宋代に頻発した自然災害の中でも、特に深刻な脅威だった蝗害に対応して出現した「駆蝗神」への信仰を考察されました。国家儀礼から地方祭祀へ、そして自然神から人格神への変化というプロセスについても、論究されていました。
〇午後 シンポジウム
午後は、「歴史のなかの独裁」と題するシンポジウムが行われました。はじめに、森丈夫先生(福岡大学)より、シンポジウムの趣旨をご説明いただきました。昨今の情勢から「独裁」への注目が集まっており、それに歴史学から応えようとするものだと述べられました。
高橋亨先生(福岡大学)からは、「臣民の声を聴く独裁君主-建言民情の処理過程を焦点として-」という題目でご発表いただきました。明代中期における「建言民情」という制度の考察を通して、一臣民の訴状にも決裁を下す「皇帝像」が皇帝本人や官僚に負担を強いた姿を描かれました。
湯浅翔馬先生(福岡大学)からは、「独裁者あるいは皇帝からの脱却-フランス第三共和政期のボナパルト派におけるナポレオン体制像の展開-」という題目でご発表いただきました。共和政が確立していく中で、党勢の衰退という事態に直面したボナパルト派は、理想としていた「ナポレオン体制」像を変容させ、最終的に「人民投票」という理念へと収斂させた様を考察されました。
熊野直樹先生(九州大学)からは、「ナチ独裁再考」という題目でご発表いただきました。ナチ独裁と民主主義の関係について、ポリアーキー論の観点からお話しをしていただきました。「少数派の人権保障の最後の砦」である司法に着目し、ナチ独裁について議論していただきました。
その後、質疑応答が行われました。報告されたお三方に再度ご登壇頂き、活発な議論が繰り広げられました。
午後は、「歴史のなかの独裁」と題するシンポジウムが行われました。はじめに、森丈夫先生(福岡大学)より、シンポジウムの趣旨をご説明いただきました。昨今の情勢から「独裁」への注目が集まっており、それに歴史学から応えようとするものだと述べられました。
高橋亨先生(福岡大学)からは、「臣民の声を聴く独裁君主-建言民情の処理過程を焦点として-」という題目でご発表いただきました。明代中期における「建言民情」という制度の考察を通して、一臣民の訴状にも決裁を下す「皇帝像」が皇帝本人や官僚に負担を強いた姿を描かれました。
湯浅翔馬先生(福岡大学)からは、「独裁者あるいは皇帝からの脱却-フランス第三共和政期のボナパルト派におけるナポレオン体制像の展開-」という題目でご発表いただきました。共和政が確立していく中で、党勢の衰退という事態に直面したボナパルト派は、理想としていた「ナポレオン体制」像を変容させ、最終的に「人民投票」という理念へと収斂させた様を考察されました。
熊野直樹先生(九州大学)からは、「ナチ独裁再考」という題目でご発表いただきました。ナチ独裁と民主主義の関係について、ポリアーキー論の観点からお話しをしていただきました。「少数派の人権保障の最後の砦」である司法に着目し、ナチ独裁について議論していただきました。
その後、質疑応答が行われました。報告されたお三方に再度ご登壇頂き、活発な議論が繰り広げられました。
以上、初日の外国史部会の様子をお伝えいたしました。報告者の皆様、ご参加いただいた皆様、運営に携わった先生方・院生・学部生の皆様、誠にありがとうございました。
外国史部会院生一同
外国史部会院生一同