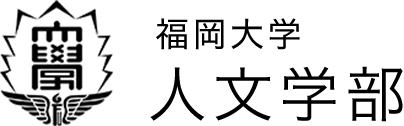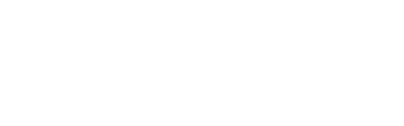学科トピックス
2025.10.28
第27回七隈史学会のレポート②です!
こんにちは、日本史教員の山田です。一気に気温が下がり、寒いくらいになってきました。
さて、今回は9月27日(土)・28日(日)に開催された第27回七隈史学会大会の様子のレポート第2弾ということで、日本史部会および公開講演の様子をお伝えします。以下、大学院生が書いてくれたレポートです。
さて、今回は9月27日(土)・28日(日)に開催された第27回七隈史学会大会の様子のレポート第2弾ということで、日本史部会および公開講演の様子をお伝えします。以下、大学院生が書いてくれたレポートです。
こんにちは。日本史専修博士課程2年の佐々木と申します。今年は「秋は短く、急に冬を感じる」との予報が出ているそうで、短い秋に尻を叩かれる形ですが、9月27日(土)に開催されました日本史部会と公開講演の様子を皆様にお届けします。
日本史部会の先頭を切ったのは、福岡大学大学院修士2年・近代史専攻の林勇希さんです。「戦後サークル運動における「山(やま)脈(なみ)の会」の歴史的意義について」という題で報告いただきました。林報告では、「山脈の会」という戦後の文化運動について、会誌『山脈』をもとに明らかにしておられました。『山脈』の一部は秋田県に所蔵されているそうで、林さんは、資料調査もさることながら、『山脈』に寄稿した方にも現地でヒアリングを実施したそうです…!林さんの行動力に感服するとともに、「オーラルヒストリー」と歴史資料の残るその土地の風土やそこに住む人々のことを知る重要性を再確認させられました。
次に、宮崎県地域史研究会の籾木郁朗さんの報告です。「南九州における大正期の私設鉄道敷設と地域社会との関わり~宮崎県・鹿児島県の路線の比較から~」という題で報告いただきました。籾木報告は、北部九州の鉄道に比べて研究蓄積が少ない、南九州の鉄道について、鉄道敷設とそれに関わった集団や個人の関係等を検討した報告でした。南九州では地元有力者が発起人となり、株主による資本提供だけではなく、経営までもが行われていたそうです。地元の地名も多く、南九州出身の方は容易にどこの路線か想起できたのではないでしょうか?
日本史部会の先頭を切ったのは、福岡大学大学院修士2年・近代史専攻の林勇希さんです。「戦後サークル運動における「山(やま)脈(なみ)の会」の歴史的意義について」という題で報告いただきました。林報告では、「山脈の会」という戦後の文化運動について、会誌『山脈』をもとに明らかにしておられました。『山脈』の一部は秋田県に所蔵されているそうで、林さんは、資料調査もさることながら、『山脈』に寄稿した方にも現地でヒアリングを実施したそうです…!林さんの行動力に感服するとともに、「オーラルヒストリー」と歴史資料の残るその土地の風土やそこに住む人々のことを知る重要性を再確認させられました。
次に、宮崎県地域史研究会の籾木郁朗さんの報告です。「南九州における大正期の私設鉄道敷設と地域社会との関わり~宮崎県・鹿児島県の路線の比較から~」という題で報告いただきました。籾木報告は、北部九州の鉄道に比べて研究蓄積が少ない、南九州の鉄道について、鉄道敷設とそれに関わった集団や個人の関係等を検討した報告でした。南九州では地元有力者が発起人となり、株主による資本提供だけではなく、経営までもが行われていたそうです。地元の地名も多く、南九州出身の方は容易にどこの路線か想起できたのではないでしょうか?
午後の部のトップバッターは、福岡大学大学院修士2年・中世史専攻・能勢かれんさんです。「文禄の役における豊臣秀吉の兵粮米政策」という題で報告いただきました。豊臣秀吉の朝鮮出兵において、兵粮の調達は最重要課題であったらしく、各領国から出兵していた諸将及び日本軍がどのように兵粮を調達していたのか、ということを検討したのが能勢報告でした。朝鮮の各地の邑城には兵粮が多くあり、朝鮮へ渡海する秀吉のために取っておいたらしいのですが、戦局が厳しくなると兵粮は諸将に開放されていたそうです。秀吉の朝鮮出兵の難しさ(実現可能だったか的な話しで)がうかがえる報告でした。
次に、志免町立志免中学校・吉田智史さんの報告です。「朝鮮通信使の海路における対馬藩の船組と乗組について」という題目で報告いただきました。吉田さんは令和5年度に九州大学大学院で博士論文を提出されており、本報告は博士論文の1章分に当たります。吉田報告は、江戸時代に唯一幕府から朝鮮とのやり取りを任された対馬藩が、どのような船団編成と人員で、通信使の先導・警固を行っていたのか、「対馬宗家文書」から明らかにした報告でした。「対馬宗家文書」は日本各地に所在があり、総数約12万点と日本屈指の量を誇る文書群ですが、吉田報告からだけでも、「友好の使者」とよく言われている朝鮮通信使は、実はその遂行に無理があったという裏事情が垣間見ることができました。
日本史部会最後の報告は、高鍋町教育委員会社会教育課・古林直基さんの報告です。「幕末維新期における延岡藩の藩政機構について-慶応4年の入京差止処分を中心に-」という題で報告いただきました。延岡藩は、朝廷から鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍側として戦闘していた、と事実誤認をされて、入京差止処分が下されていたそうです。古林報告では、その処分に対応した延岡藩の上方(京都・大坂)の藩組織について、その内実を検討されておりました。
次に、志免町立志免中学校・吉田智史さんの報告です。「朝鮮通信使の海路における対馬藩の船組と乗組について」という題目で報告いただきました。吉田さんは令和5年度に九州大学大学院で博士論文を提出されており、本報告は博士論文の1章分に当たります。吉田報告は、江戸時代に唯一幕府から朝鮮とのやり取りを任された対馬藩が、どのような船団編成と人員で、通信使の先導・警固を行っていたのか、「対馬宗家文書」から明らかにした報告でした。「対馬宗家文書」は日本各地に所在があり、総数約12万点と日本屈指の量を誇る文書群ですが、吉田報告からだけでも、「友好の使者」とよく言われている朝鮮通信使は、実はその遂行に無理があったという裏事情が垣間見ることができました。
日本史部会最後の報告は、高鍋町教育委員会社会教育課・古林直基さんの報告です。「幕末維新期における延岡藩の藩政機構について-慶応4年の入京差止処分を中心に-」という題で報告いただきました。延岡藩は、朝廷から鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍側として戦闘していた、と事実誤認をされて、入京差止処分が下されていたそうです。古林報告では、その処分に対応した延岡藩の上方(京都・大坂)の藩組織について、その内実を検討されておりました。
日本史部会の報告が終わってから、皆さんお待ちかね、東京大学史料編纂所・名誉教授の横山伊徳先生の公開講演がありました。横山先生のご専門は、19世紀日本とオランダの関係についてであり、東京大学史料編所の所長を歴任されました。今回は「幕末条約港貿易体制の形成と西南諸藩」という題でご講演いただきました。「グローバルヒストリー」という視点がよく叫ばれるなか、今回は貿易利潤などによる「富」という視点からご講演いただきました。こうした視点は、横山先生が従来抱かれていた興味関心について、今回ご講演された大変貴重なご講演になったかと思われます。
第21回大会(2019年)ぶりの文系センター棟での開催でしたが、一般の方はもちろん多くの学部生も参加されていました。ご参加いただいた皆様、また、報告者の皆様、運営に携わった先生方・院生の皆様、最後に、ご講演いただきました横山先生に感謝申し上げます。
第21回大会(2019年)ぶりの文系センター棟での開催でしたが、一般の方はもちろん多くの学部生も参加されていました。ご参加いただいた皆様、また、報告者の皆様、運営に携わった先生方・院生の皆様、最後に、ご講演いただきました横山先生に感謝申し上げます。