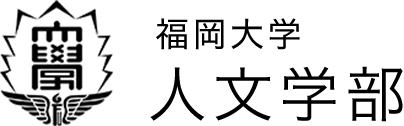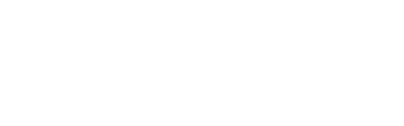学科トピックス
2025.09.11
2年生対象の研修バスハイクに行ってきました!
こんにちは、日本史教員の山田です。9月半ばとなりましたが、暑い日がつづきます。そうした中、本学では昨日から後期授業がはじまりました。夏休みの間にひとまわり成長したであろう皆さんに会うのが楽しみです!
さて、その夏休みの後半、9月4日(木)から5日(金)にかけて、歴史学科では2年生を対象とする研修バスハイクを1泊2日で実施しました。本学の歴史学科では、2年生から日本史・東洋史・西洋史・考古学にわかれて、各専修に関する授業を中心に受けるようになります。専門性の高い知識と技能を身につけるためのカリキュラムで、それこそが本学の歴史学科の特徴であり、強みであるわけですが、一方で他専修の学生と交流する機会が減ってしまうという実態もあります。専修を越えた学問的・人的交流を図る機会をなんとかつくれないか、ということで、今回はじめて2年生を対象とする研修バスハイクを企画してみました。どれほど参加者が集まるかわかりませんでしたが、最終的には2年生22名と教員3名で出発することになりました。
さて、その夏休みの後半、9月4日(木)から5日(金)にかけて、歴史学科では2年生を対象とする研修バスハイクを1泊2日で実施しました。本学の歴史学科では、2年生から日本史・東洋史・西洋史・考古学にわかれて、各専修に関する授業を中心に受けるようになります。専門性の高い知識と技能を身につけるためのカリキュラムで、それこそが本学の歴史学科の特徴であり、強みであるわけですが、一方で他専修の学生と交流する機会が減ってしまうという実態もあります。専修を越えた学問的・人的交流を図る機会をなんとかつくれないか、ということで、今回はじめて2年生を対象とする研修バスハイクを企画してみました。どれほど参加者が集まるかわかりませんでしたが、最終的には2年生22名と教員3名で出発することになりました。
 筑前町立大刀洗平和記念館に到着
筑前町立大刀洗平和記念館に到着 最初に大刀洗飛行場の概要説明
最初に大刀洗飛行場の概要説明 戦闘機の防空壕「掩体壕」も訪れました
戦闘機の防空壕「掩体壕」も訪れました
最初に訪れたのは、筑前町立大刀洗平和記念館です。ここは、戦前につくられた大刀洗飛行場とその周辺に成立していた軍都的景観をいまに伝える博物館施設です。戦争の影響を強く受けていた近代の地域の歴史を知るのみならず、特攻隊の出撃状況などについても詳しい説明があります。
 まずは館の概要説明
まずは館の概要説明 重光葵展の解説。皆さん熱心!
重光葵展の解説。皆さん熱心! BBQ、お腹いっぱいいただきました
BBQ、お腹いっぱいいただきました
大刀洗平和記念館を出発して、大分に向かいます。予定では初日に臼杵市へ向かい、国宝「臼杵石仏」を見学する予定でしたが、前日に発生した「いきなり台風」の影響を避けるために、スケジュールを変更して大分市内の大分県立先哲史料館を訪れました。ここは大分県出身の歴史的人物にスポットをあて、その調査や研究、展覧会企画、書籍の刊行等を行っている博物館施設です。今回訪れたタイミングでは、戦後80年ということで、大分県出身の外交官重光葵の特別展が開催されていました。日本の「降伏文書」にサインした外交官です。主幹研究員の松原さんに展示解説いただきましたが、その「降伏文書」原本も展示されており、皆さんとても熱心に聞き入っていました。そして、この後は大分県立美術館を訪れ、18時くらいに宿泊先に到着しました。夜はみんなでBBQ!楽しく過ごせました。
 発掘現場の事務所でまずは概要説明
発掘現場の事務所でまずは概要説明 整備された庭園遺構の説明
整備された庭園遺構の説明 輸入陶磁器から豊後府内の繁栄がうかがえます
輸入陶磁器から豊後府内の繁栄がうかがえます
2日目は快晴となり、予定どおりに大分市内の国史跡・大友氏館跡へ。1998年の発掘調査で発見された戦国大名大友氏の居館を発掘し続けている現場で、大分市教育委員会の五十川さん、山本さん、広津留さんに、史跡整備の経緯から最新の発掘・研究の成果に至るまで、わかりやすく解説していただきました。ちなみに、五十川さんは本学歴史学科の出身。山田の同級生です!
大友氏館跡の現場を見た後は、その出土品を見てみよう、ということで大分県立埋蔵文化財センターに向かいます。ここでは調査第一課長の横澤さんに、しっかり解説いただきました。
大友氏館跡の現場を見た後は、その出土品を見てみよう、ということで大分県立埋蔵文化財センターに向かいます。ここでは調査第一課長の横澤さんに、しっかり解説いただきました。
 摩崖仏の特徴について解説いただきました
摩崖仏の特徴について解説いただきました 今回2度目の記念写真
今回2度目の記念写真 臼杵城についても、詳しく解説いただきました
臼杵城についても、詳しく解説いただきました
2日目午後は臼杵市に移動し、国宝「臼杵石仏」を拝観します。ここには、平安時代末期から鎌倉時代にかけて自然の岩壁・露岩に彫られた61躯の仏像群が点在します。臼杵市教育委員会の鎌谷さんと山田さんにご案内いただきました。関連する文献史料はなく、制作事情ははっきりしていませんが、とにかくその大きさと数、彫刻の技量に圧倒されます。また、直接岩肌に彫られているため、保全のための温度管理等の作業が必要だという話も、たいへん印象にのこりました。
そして、最後に、大友宗麟や臼杵藩主稲葉家の居城となった臼杵城をめぐりました。この城、いまいくと地続きとなっていますが、かつては「丹生島」という島につくられたお城でした。そうした城の歴史や特徴、こんにちまで残されている櫓等のことについて、臼杵市教の山田さんに解説いただきました。ちなみに、山田さんも本学歴史学科の出身です!
こんな感じで、1泊2日の研修バスハイクを無事に終えることができました。参加者の皆さん、それぞれ学びや気づきのある2日間になったのではないでしょうか。また、同級生と改めて交流するいい機会にもなったと思います。そして、台風が接近する中、スケジュール調整に対応いただいたうえ、しっかりと解説・案内をいただいた皆さんに、改めて心から感謝申し上げます!ありがとうございました!!
そして、最後に、大友宗麟や臼杵藩主稲葉家の居城となった臼杵城をめぐりました。この城、いまいくと地続きとなっていますが、かつては「丹生島」という島につくられたお城でした。そうした城の歴史や特徴、こんにちまで残されている櫓等のことについて、臼杵市教の山田さんに解説いただきました。ちなみに、山田さんも本学歴史学科の出身です!
こんな感じで、1泊2日の研修バスハイクを無事に終えることができました。参加者の皆さん、それぞれ学びや気づきのある2日間になったのではないでしょうか。また、同級生と改めて交流するいい機会にもなったと思います。そして、台風が接近する中、スケジュール調整に対応いただいたうえ、しっかりと解説・案内をいただいた皆さんに、改めて心から感謝申し上げます!ありがとうございました!!