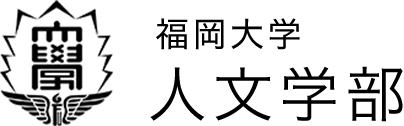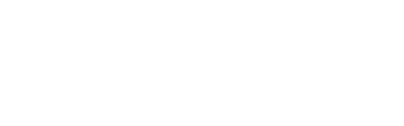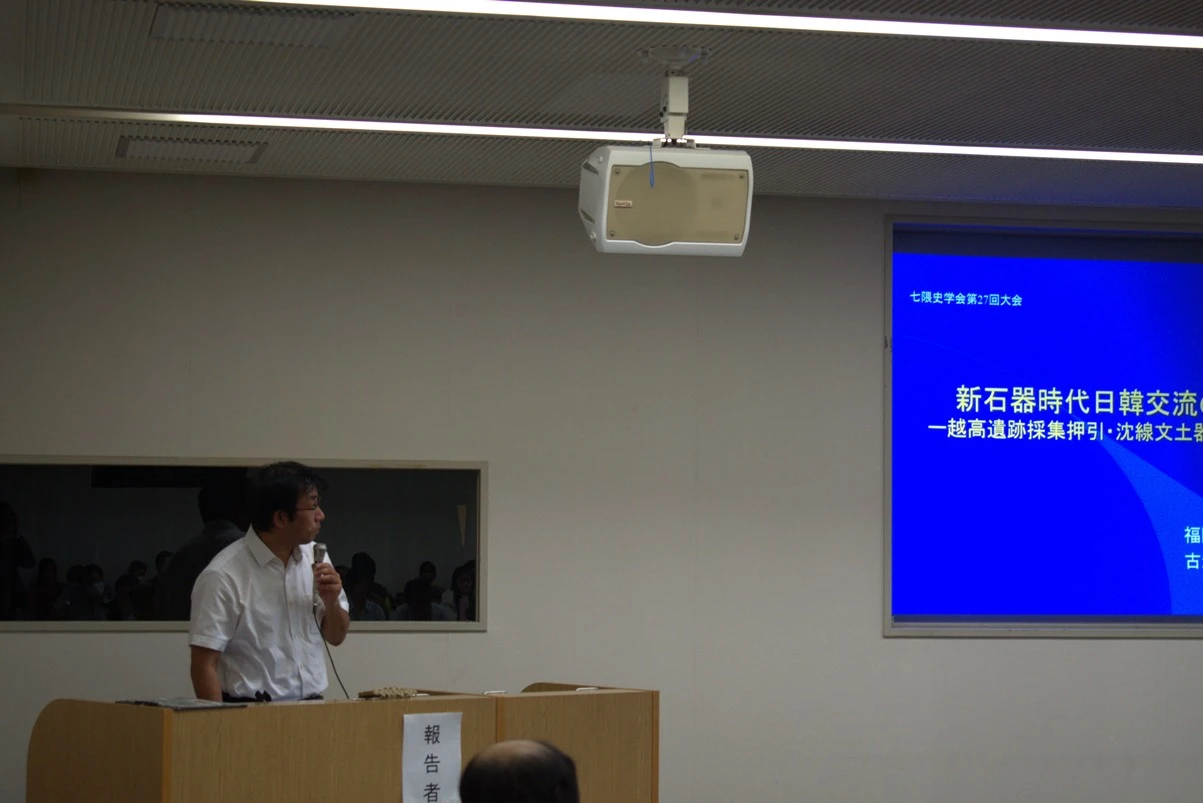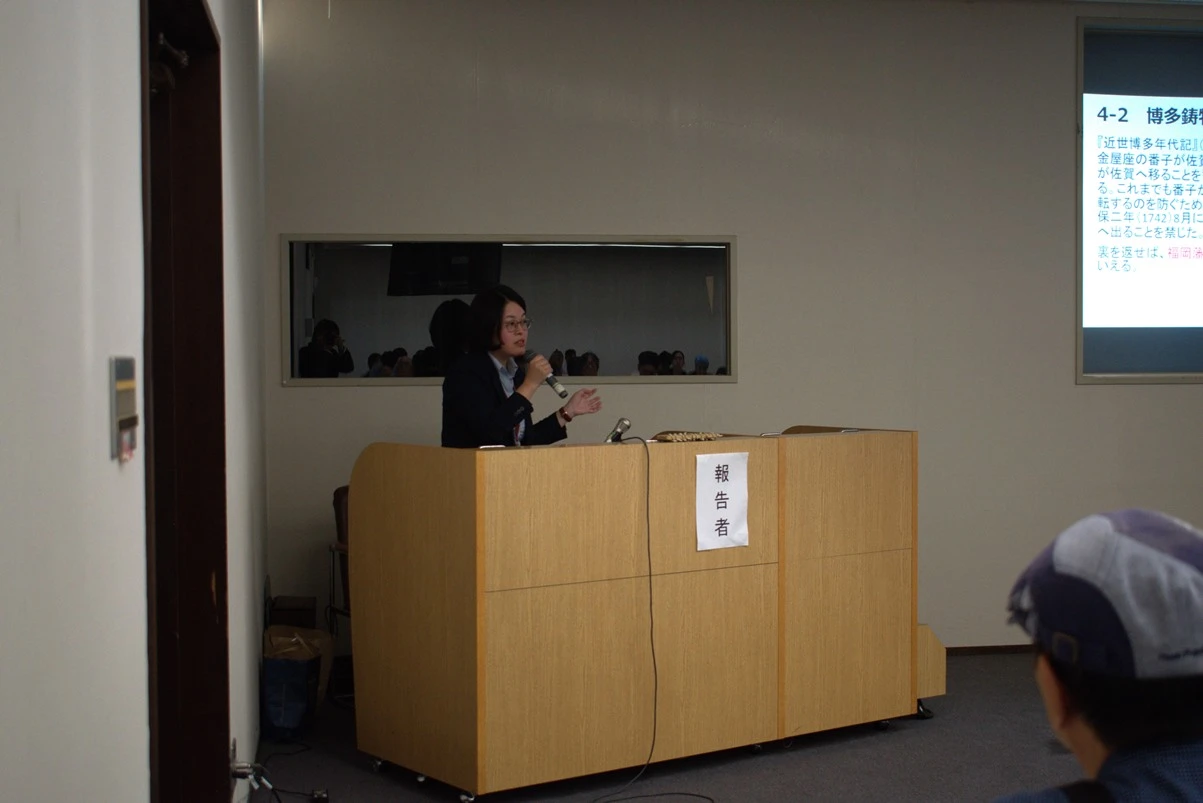学科トピックス
2025.11.07
第27回七隈史学会のレポート③です!
こんにちは、日本史教員の山田です。今回は9月27日(土)・28日(日)に開催された第27回七隈史学会大会の様子のレポート第3弾ということで、考古部会の様子をお伝えします。以下、大学院生が書いてくれたレポートです。
考古部会です。考古部会は9月28日の日曜日の大会二日目に行われました。今年は公開講演にて横山伊徳先生が「幕末条約港貿易体制の形成と西南諸藩」という題目で発表されることから、対外交渉・交流をテーマに各報告者から発表していただきました。
1番目は釜山大学博物館の廣瀬雄一さんです。廣瀬さんは「対馬海峡をめぐる新石器時代交流の新展開」という題目で報告されました。近年、対馬島では縄文時代早期の繊維土器、石銛、塞ノ神式土器など新石器時代早期-縄文時代早期の交流を考える上で重要な資料が発見されています。報告では、新資料を含めた縄文時代早期~後期の交流を検討し、縄文時代時代早期末からの温暖化に伴い、生計戦略が変化して隆起文土器の南下が起きることや東三洞貝塚や上老大島出土の縄文土器から縄文時代前期以降にも土器製作に韓半島の影響があるという新しい視点を示されました。
2番目は福岡大学の古澤義久さんです。古澤さんは「新石器時代日韓交流の様相-越高遺跡採集沈線・押引文土器を中心に-」という題目で報告されました。対馬島の越高・越高尾崎遺跡は出土した土器のほとんどが韓半島の土器であることや韓半島に類例がある方形炉が見つかったことから韓半島からの集団の居住地とされています。本遺跡で採集された土器には韓半島の土器とする説、縄文時代早期の土器とする説、縄文時代前期の土器とする3説があり、本資料の再検討から縄文時代早期後葉~前期前葉-新石器時代早・前期の交流様相が深いことが分かり、研究の深化の重要性が示されました。
3番目は佐賀大学の重藤輝行さんです。重藤さんは「旧糟屋郡北部の渡来人と粕屋屯倉」という題目で報告されました。福岡県古賀市流遺跡からは5世紀初頭~前半のタタキ文土器(軟質土器)、陶質土器、竈、5世紀後半の排水溝付住居が見つかっており、周辺遺跡の渡来系遺物・遺構を含めて当地域に朝鮮半島からの渡来人が存在した事が分かっています。6世紀初頭には須恵器と技法や形態に差異がある土器やタタキを施す土師器が出土していることから当地で渡来人が土器生産に関係していたが可能性があり、6世紀中頃以降も朝鮮半島と同様の土器生産・供給が行われ、粕屋屯倉の経営、6世紀末の船原古墳築造との関係性することが分かりました。
1番目は釜山大学博物館の廣瀬雄一さんです。廣瀬さんは「対馬海峡をめぐる新石器時代交流の新展開」という題目で報告されました。近年、対馬島では縄文時代早期の繊維土器、石銛、塞ノ神式土器など新石器時代早期-縄文時代早期の交流を考える上で重要な資料が発見されています。報告では、新資料を含めた縄文時代早期~後期の交流を検討し、縄文時代時代早期末からの温暖化に伴い、生計戦略が変化して隆起文土器の南下が起きることや東三洞貝塚や上老大島出土の縄文土器から縄文時代前期以降にも土器製作に韓半島の影響があるという新しい視点を示されました。
2番目は福岡大学の古澤義久さんです。古澤さんは「新石器時代日韓交流の様相-越高遺跡採集沈線・押引文土器を中心に-」という題目で報告されました。対馬島の越高・越高尾崎遺跡は出土した土器のほとんどが韓半島の土器であることや韓半島に類例がある方形炉が見つかったことから韓半島からの集団の居住地とされています。本遺跡で採集された土器には韓半島の土器とする説、縄文時代早期の土器とする説、縄文時代前期の土器とする3説があり、本資料の再検討から縄文時代早期後葉~前期前葉-新石器時代早・前期の交流様相が深いことが分かり、研究の深化の重要性が示されました。
3番目は佐賀大学の重藤輝行さんです。重藤さんは「旧糟屋郡北部の渡来人と粕屋屯倉」という題目で報告されました。福岡県古賀市流遺跡からは5世紀初頭~前半のタタキ文土器(軟質土器)、陶質土器、竈、5世紀後半の排水溝付住居が見つかっており、周辺遺跡の渡来系遺物・遺構を含めて当地域に朝鮮半島からの渡来人が存在した事が分かっています。6世紀初頭には須恵器と技法や形態に差異がある土器やタタキを施す土師器が出土していることから当地で渡来人が土器生産に関係していたが可能性があり、6世紀中頃以降も朝鮮半島と同様の土器生産・供給が行われ、粕屋屯倉の経営、6世紀末の船原古墳築造との関係性することが分かりました。
4番目はKudan株式会社の佐々木雄一郎さんと株式会社水上洋行の久保田偉史さん、寺戸隆幸さんに「最新の測量機器(XGRIDS)を用いた3Dの計測と活用について」という題目で報告していただきました。会場にて実演して頂きました測量器のXGRIDSは、スキャナーを手に持って歩くだけで標高、座標データの記録を行なうことが可能です。本報告は、発掘調査や史跡整備、災害復旧工事における3D測量やこれらからの文化財の未来について考えさせられる発表でした。
5番目は福岡大学の桃﨑祐輔先生です。桃﨑先生は「筑後川流域からみた対外交渉-古墳時代から中世の様相-」という題目で報告されました。大陸との玄関口である玄界灘沿岸の対外交渉と比べて有明海沿岸の対外交渉は2次的なものと軽視しがちでありますが、初期の須恵器窯跡、渡来系集団の墓、古代の杷木神籠石の築城、筑後国府のイスラム陶器、中世の貿易陶磁器・棒状鉄素材など様々な遺構や遺物から対外交渉の様相が分かります。また、中世には久留米市長門石の碇石から干満差の大きい有明海を避け、宋船が筑後川を遡上して着岸していたと考えられ、立地環境に合わせた対外交渉が行われていたことが分かります。
6番目は早稲田大学の田中史生先生です。田中先生は「志々伎神社の薩摩塔と浙江の石塔-銘文比較を中心に-」という題目でご報告されました。薩摩塔は13・14世紀に九州北西部と南西部を中心に分布する中国的意匠が施された石塔であり、石材の多くに中国寧波の梅園石が使用されることから中国商人とかかわる石塔と考えられています。その中でも銘文を有する長崎県平戸市の志々伎神社薩摩塔と薩摩塔に関連する中国石塔の銘文を比較することで現世利益を追求する中国江南七佛塔信仰と日本中世信仰の共通性、密教五仏と多宝塔を結びつけた受容があり、こうした中国石塔文化と日本中世の信仰の結合の背景には九州を生活基盤とした中国系の人々の存在があるということです。
7番目の発表は沖縄県立芸術大学大学院の景山千裕さんです。景山さんは「波戸岬採集資料から考える中世の海上交易」という題目で報告されました。 佐賀県唐津市波戸岬では多量の14-15世紀の元末から明時代の陶磁器が採集されており、周辺に同時期の陸上遺跡や港が見られない点から沈船に伴う可能性が高いと見られています。本資料は青磁碗を主体に、青磁盤、香炉、白磁皿、天目茶碗、茶入、水注が含まれており、同時期の遺跡に見られる青磁皿や壺類、青磁碗に直口、雷文の碗が含まれないことから下限の年代が遅くとも15世紀前半に位置づけられる事が分かりました。また、沈船関係資料から喫茶道具が一定量見つかった事例は他に無く、中国の貿易陶磁器集積遺跡から灰被タイプの天目茶碗や薄胎の茶入れの出土は確認されず、福州から琉球への沈船である東洛島沈船から灰被タイプの天目茶碗が出土していることから福州→琉球→博多という経路で運ばれた可能性が高いことが分かりました。
5番目は福岡大学の桃﨑祐輔先生です。桃﨑先生は「筑後川流域からみた対外交渉-古墳時代から中世の様相-」という題目で報告されました。大陸との玄関口である玄界灘沿岸の対外交渉と比べて有明海沿岸の対外交渉は2次的なものと軽視しがちでありますが、初期の須恵器窯跡、渡来系集団の墓、古代の杷木神籠石の築城、筑後国府のイスラム陶器、中世の貿易陶磁器・棒状鉄素材など様々な遺構や遺物から対外交渉の様相が分かります。また、中世には久留米市長門石の碇石から干満差の大きい有明海を避け、宋船が筑後川を遡上して着岸していたと考えられ、立地環境に合わせた対外交渉が行われていたことが分かります。
6番目は早稲田大学の田中史生先生です。田中先生は「志々伎神社の薩摩塔と浙江の石塔-銘文比較を中心に-」という題目でご報告されました。薩摩塔は13・14世紀に九州北西部と南西部を中心に分布する中国的意匠が施された石塔であり、石材の多くに中国寧波の梅園石が使用されることから中国商人とかかわる石塔と考えられています。その中でも銘文を有する長崎県平戸市の志々伎神社薩摩塔と薩摩塔に関連する中国石塔の銘文を比較することで現世利益を追求する中国江南七佛塔信仰と日本中世信仰の共通性、密教五仏と多宝塔を結びつけた受容があり、こうした中国石塔文化と日本中世の信仰の結合の背景には九州を生活基盤とした中国系の人々の存在があるということです。
7番目の発表は沖縄県立芸術大学大学院の景山千裕さんです。景山さんは「波戸岬採集資料から考える中世の海上交易」という題目で報告されました。 佐賀県唐津市波戸岬では多量の14-15世紀の元末から明時代の陶磁器が採集されており、周辺に同時期の陸上遺跡や港が見られない点から沈船に伴う可能性が高いと見られています。本資料は青磁碗を主体に、青磁盤、香炉、白磁皿、天目茶碗、茶入、水注が含まれており、同時期の遺跡に見られる青磁皿や壺類、青磁碗に直口、雷文の碗が含まれないことから下限の年代が遅くとも15世紀前半に位置づけられる事が分かりました。また、沈船関係資料から喫茶道具が一定量見つかった事例は他に無く、中国の貿易陶磁器集積遺跡から灰被タイプの天目茶碗や薄胎の茶入れの出土は確認されず、福州から琉球への沈船である東洛島沈船から灰被タイプの天目茶碗が出土していることから福州→琉球→博多という経路で運ばれた可能性が高いことが分かりました。
8番目は福岡大学人文学部歴史学科助手の大重優花さんです。大重さんは「近世北部九州の鋳物師と日韓混交型式鐘の拡散」という題目で報告されました。梵鐘(寺社の鐘)には、日本で製作された「日本鐘」朝鮮半島で製作された「朝鮮鐘」異なる様式装飾を導入した「混交型式鐘」があり、戦国~江戸時代前期までは芦屋鋳物師を中心に「日韓混交型式鐘」が製作されました。江戸時代前期以降の芦屋鋳物師の博多への移動に伴い、他の博多鋳物師にもヘラ押しによる施文などの技法が伝播し、長崎警備や番子の逃走により佐賀藩の鋳物師にも伝播しました。近世以降、職人の編成、多くの技術書の出現により各地で中世までの技術(在来知)の共有化が進み、在来知が幕末における青銅大砲製作に繋がるというものでした。
その他にも、昼休憩の時間で福岡市史跡整備活用課の神啓崇さん、鹿児島大学大学院の住吉太郎さん、福岡大学大学院生の井内達也さん、同学部生の日永田晟諒さん、佐藤萌美さん、東司ちひろさんの6名にポスターセッションを行っていただきました。本年度の発表は学生が多く、研究会の発表に向けて良い発表練習の場になったと思います。
その他にも、昼休憩の時間で福岡市史跡整備活用課の神啓崇さん、鹿児島大学大学院の住吉太郎さん、福岡大学大学院生の井内達也さん、同学部生の日永田晟諒さん、佐藤萌美さん、東司ちひろさんの6名にポスターセッションを行っていただきました。本年度の発表は学生が多く、研究会の発表に向けて良い発表練習の場になったと思います。
本年度も多くの方に足を運んでいただき、資料集も100冊以上配布されました。コロナで一度断絶した諸外国との合同研究・学会が今後さらに発展することを期待し、我々もその一端を担えるように努力する所存です。今後とも応援よろしくお願いいたします。
福岡大学考古学研究室一同
福岡大学考古学研究室一同